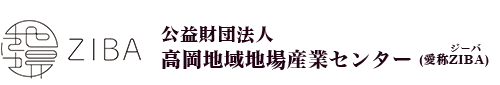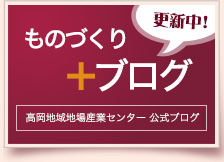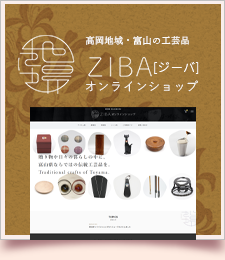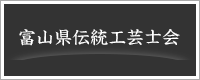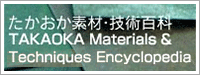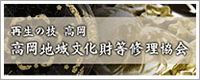桂樹舎さんに行ってきました♪その2
越中和紙
前の記事で、防染糊を置いてから染めるところまでを
ざっと紹介してみましたが、
その後糊はどうなるのか、だって桂樹舎さんの和紙って白いところも多いし? ?
?
と思ってらっしゃる方もおられることと思います。
有り体にいいますと、防染糊は落とします。
防染糊と言うだけあって、その部分を染めないことが目的の糊なので
(マスキングテープみたいなものですね)
染めたら糊を落として、その部分が白くなります。
(そもそも、型染めとか防染糊って何?とおっしゃる方は、過去記事「型染め?」へ)
…え?
だからどうやって落とすのかが問題だ??
そう。
そこが和紙の強さを感じる一つのポイントでもあるのです。

ご覧ください、こちらが「水元(みずもと)」と言われる、糊落としの作業。
水槽の中に染めた紙を浸け、手で水をすくって水流で洗い落としていく感じです。
手元付近の水面がけっこう動いているのがご覧いただけると思いますが、
動画でご紹介したいくらい、けっこう激しい水流です。
しかーし、この水元の作業では、和紙は破れたりしないのです。

糊が落ちてくると、こんな風に。
水の中での発色が、いちばんきれいだと言います。
糊置きしてから時間をかけすぎると、固まりすぎて落ちづらくなるのだそう。
糊や顔料を乾かす時間は必要ですが、ほどよいタイミングを見計らって
効率よく作業していくのも熟練の技。
ちなみに桂樹舎さんの水元用の水槽は、井戸水が使用されているだけでなく、
蒸気を通すパイプが仕込んであって、冬場は少し温めて使ったりもするそう。
手に優しい設備ができあがっていました

糊を落とした紙は、またこうして吊って、最後の乾燥に入ります。
洋紙と違って、水に浸けてもきれいに真っ直ぐ乾くのも、楮紙の魅力の一つです。
この後カレンダーは12か月分と表紙をまとめて綴り、また筒や箱物、カバー類などは
形を作る工程へと進んでいきます。